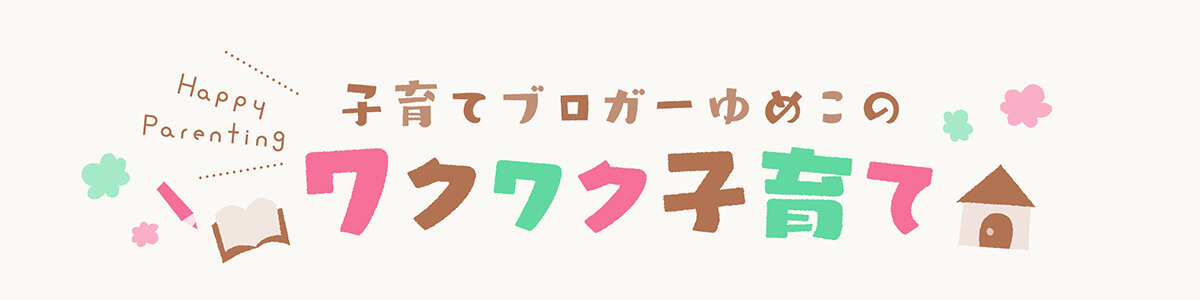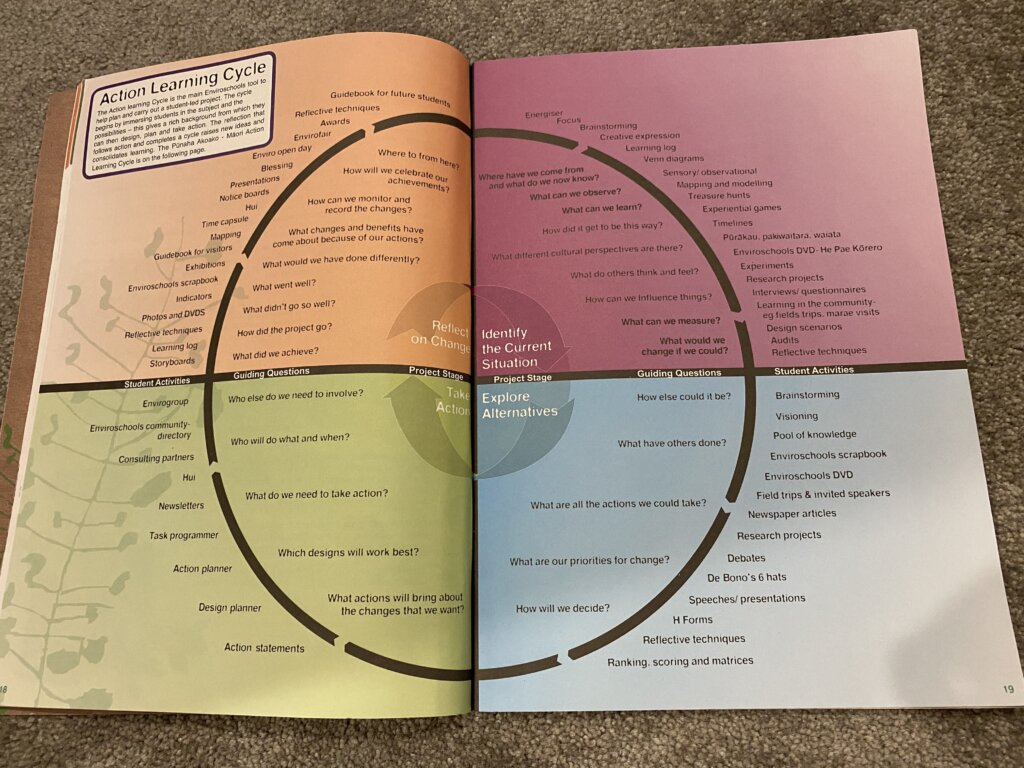ニュージーランドのゆめこ(@BloggerYumeko)です。
この記事はこんな方におすすめ
-
- ニュージーランドのインクルーシブ教育について知りたいあなた
- ニュージーランドの保育について興味のあるあなた
- ニュージーランドと日本のインクルーシブ教育の違いについて知りたいあなた
1.ニュージーランドのインクルーシブ教育に対する自身の定義と理解
インクルーシブ教育の定義としては、バックグラウンドの違う全ての子どもたちが、同じ場で学ぶことと理解しています。
同じ場といっても、皆が同時に同じことを学ぶ(する)のではなくて、その一人一人にあった学習プログラムを提案、提供していくことだと理解しています。
2.幼児教育現場でのインクルーシブ教育取り組みやイニシアティブ
ニュージーランドの、幼児教育のカリキュラムである、テファリキの中にはこのような文章があります。
Te whāriki, Strand 3, Contribution/Mana tangata
There are equitable opportunities for learning irrespective of gender, ability, age, ethnicity or background.
性別、能力、年齢、カルチャー(民族)、背景に関係なく、平等に学習の機会が与えられます。
https://yumeko-kosodate.com/tewhariki/
NZの幼児教育プログラムテファリキについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ
ニュージーランドの幼児教育機関ではこのテファリキを使ったプログラムを駆使していくことが必須となっています。
そのテファリキの中で掲げられている、5つの要素の一つコントリビューション・contributionの中に上記の記載があります。
このゴールがニュージーランド、幼児教育現場でのインクルーシブ教育のあり方を簡潔にまとめて、説明していると思います。
私たちは、園の設備で受け入れ可能な障害のあるお子さん(children with special needs/ neurodevelopmental disorders)の受け入れをしています。
例えば、ADHD・注意欠如多動症、Autism ・自閉症、Dyslexia・発達性読み書き障害、HSP(Highly Sensitive Person)・とても繊細、Speech Delay・言葉の遅れなどをもつ子どもたちです。
それに加え、ニュージーランドは多国籍国家なので、様々な民族の子どもたちが混在しています。
今現在私の園では15カ国以上の違うカルチャーの子どもたちが学びを共にしています。
3.支援が必要な生徒へのサポート体制
MoE (Ministry of Education) 教育省と提携し、スペシャリストのサポートを受けつつ、教員、親が一眼となりお子さんのサポートを進めていきます。
例えば障害のあるお子さんの受け入れの場合、MoE からESW(Education support workers) 特別支援の先生を割り当ててもらえるようにします。
申し込み志願書(application form)を作成しMoEに提出します。その時間の割り当ては、それぞれのケースと審査の結果によって変わってきます。
例えばA君には週に8時間のESW のサポートがつきますなどです。
子どものIDP (Individual Development Plan )と呼ばれる、 個人の成長計画書の作成をします。
幼稚園から小学校への移行(transition to school)も小学校の新入生受け入れクラスの先生と連携をとり、それぞれのお子さんにあったスムーズな移行ができるようにします。例えば、通常では5歳の誕生日を迎える前に、2、3回のスクールビジット(鳴らし入学・学校訪問)だけを行います。
しかし特別に支援の必要なお子さんの場合は準備期間が数週間、または数ヶ月にわたる場合もあります。
4.教師間でのインクルーシブ教育の学習環境の促進のために心がけていること
モーニングフイ (morning hui)と呼ばれる朝のミィーティングを毎日おこなっています。園児が登園してくる前の時間帯、毎朝45分間がそのミィーティングにあてられます。
このモーニングフイはマオリのカラキア・Karakia (お祈り)とワイアタ・waiata(マオリ語の唄)ではじまります。
このミィーティングでは、それぞれの子ども達への教員の対応の仕方、アプローチの手順などを詳しく話し合います。
全ての子どもはユニークで、それぞれが違う考え方、価値観を保持しているということを常に忘れないように心がけています。
教員はできるだけ既成概念にとらわれず、各々の子どもたちと関わるようにします。
例えば、同じカルチャーの子ども、もしくは親でも、その家族により違う価値観が存在するなど。
また Eurocentric normsヨーロッパ中心的・KIWI中心な考えだけではなく、ニュージーランドでマイノリティになりがちな他のカルチャーの視点も大事にするように教員同士で声をかけあっています。
最新の情報や、他の幼児教育機関の取り組みを学ぶために、積極的に勉強会にも参加しています。
5.インクルーシブ教育が園全体にあたえるポジティブな影響とは
色々なバックグラウンドをもつ子どもたち(障害のある子どもも含め)が同じ場所で学びを共にしているため、子どもたちは、皆違っていて当たり前ということを日常の中で学んでいます。
例えば、障害のある子たちが、マットタイム(皆で座って行うグループの時間)で皆と違う風に参加していたり、参加できない場合、それはその子達なりの学びの形であるのでOKという認識ができています。
又、子どもたち自身が、障害のある子達を避けたり、嫌がったりするのではなく、どのように皆で楽しい学びの環境作りをしていけるかということを、自身で考えて、作っていける手助けをしています。
私の園ではManaakitanga(他へのリスペクト、他人を気遣う優しい心、寛容性)を特に重視して子どもたちに伝えるようにしています。
6.インクルーシブ教育の実現にむけての課題や困難な経験
レシオ・ratio(子どもと教員の人数の比率)の関係でどうしても、支援の必要な子どもたちの人数があまりにも増えると、その分教員にどうしても負担がかかってしまいます。
同じように、支援の必要な子どもたちのために教員の時間を使いすぎてしまうと、その他の子供たちへの対応が手薄になってしまうことがあるために、バランスをとるように教員同士で気をつけているのが現状です。
また、障害のあるお子さん(children with special needs/ neurodevelopmental disorders) の対応には特別な知識、経験を要します。そのためにスペシャリストや色々な機関の手助けが必要になってきます。
その協力を思うように得られないケースもでてきます。
他の園児のファミリーからの批判など(これは日本に比べると、とても少ないかと思われますが、全くないとは言えません。)
7.生徒や保護者からのフィードバックをどのように収集し、反映しているか
オンラインプラットフォーム、ストーリーパーク・Storypark(子どもたちの学びをラーニングストーリーという、ニュージーランドならではでの成長記録をオンライン上に掲載するアプリ)の使用
保護者、子どもたちは携帯、ラップトップで閲覧できフィードバックも自由に書き込めます。国外在住の祖父母や親戚と、シェアすることも可能です。
https://yumeko-kosodate.com/learningstory/
ラーニングストーリーについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ
https://yumeko-kosodate.com/ece-portfolio/
ポートフォリオについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ
送迎の際に、保護者の方とできるだけお子さんの情報交換をするようにしています。
保護者さんと個別に、園でのミィーティングを設けることもあります。
限られたお子さんだけになりますが、ホームビジット・home visit、家庭訪問も行います。
- コミュニティイブニング・Community evenings
- カルチャーデイ・cultural day
- サステイナブルイベント・sustainable events
などを定期的に開催して、保護者さんとの交流、意見交換をしています。
- アンケート・questionnaire
- ニュースレター・Newsletter
- メール・Email
Parents & Whānau Support Group 日本のPTAのようなものが存在し、数名の親が定期的にミィーティングを行い、プログラムに関わっています。
子どもたちの意見・Child’s voiceはラーニングストーリーや園のディスプレイなどに掲載され、プログラムに反映されます。
8.インクルーシブ教育が今後どのような役割をはたすべきか
ニュージーランドの幼児幼児教育現場では、インクルーシブ教育は新しい概念ではありません。
私がニュージーランドで幼児教育現場に関わり始めた20年前にもすでに存在していました。
これからも、さらに違うバックグラウンドをもった全ての子どもたちが、平等な学びの場で成長していけるよう、基本的な環境作り、援助・支援の時間を増やす、教員の知識の向上などが課題になってくるかと思います。
日本の教育システムのことを考えると、多様性が認められる社会作りの基盤になってくると思います。
(注釈)
私の勤務先のオークランド公立幼稚園での取り組みをベースにお答えしています。
ご意見、ご質問のある方はこの記事の下のコメント欄からどうぞ。
ブログ内のお問い合わせからもメッセージを送って頂けます。